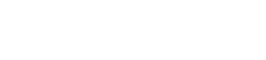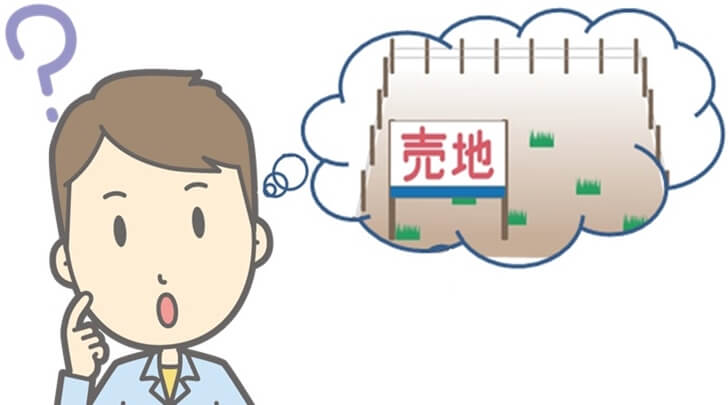
■ 土地の購入で損をしたくない人
■ 家づくりで失敗や後悔したくない人
こんにちは!建築士のしみゆうです。
購入した土地の「実際の面積」が「契約書の面積」よりも狭い!?
「まさか、そんなことあるハズが・・」と、思われたかもしれませんが、笑い事じゃありませんよ。
と言うのも、せっかくマイホームを建てるための土地を購入したのに、こんなトラブルを抱えてしまう人が後を絶たないんです。
それも、「悪徳不動産業者に騙された」などではなく、法に則った正規の土地売買でも起こり得るので、手が負えません。
しかも、その原因は「買主の知識不足」や「不動産業者の説明不足」だったりするため、その旨の記載がある契約書にサインしてしまうと、泣き寝入りするしかないのが現実なんです。
今回は、購入する土地の面積の取り決めに関わる、「公簿売買」と「実測売買」「併用売買」についてご紹介します。
土地の公簿売買とは
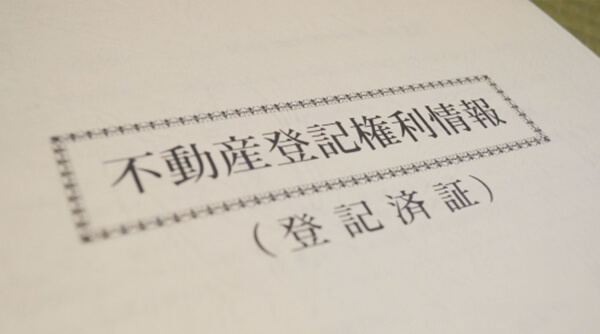

土地の面積って、持ち主の名前なんかと一緒に登録されているんじゃないんですか?

たしかに日本では、「土地」や「建物」といった不動産の「場所」や「面積」「持ち主」などの情報を登記(登録)しておけば、権利の保全を図ることができるのですが、
「登記簿に記載された土地の面積」と「実際の土地の面積」が同じとは限りませんよ。

エ~ッ!!
ちゃんと登録してあっても、実際の土地の面積と違うことがあるんですか!
「土地や建物の登記」と聞くと、なんだか難しそうだし、公のものだから信憑性が高いと思われがちですが、
登記されている土地の中には、精度の低い測量技術で作成された、古い地図(古いものは明治時代)を基にしているものも少なくありません。
実際に、「登記簿では200㎡で記載されているのに、実測したら170㎡しかなかった」や「500㎡と登記されていた土地を測ってみたら600㎡もあった」なんて話もあるくらいです。
土地の面積が思っていたより広ければ、「ラッキー!」で済むかもしれませんが、
もし狭かったら目も当てられませんし、計画していたマイホームが建てられないようなことになると一大事ですよね。

実は、こんなことが実際に起こってしまうかもしれないのが「公簿売買」と呼ばれる土地の売買方法なんです。

「公簿売買」?
「公簿売買」とは、「法務局」や「インターネット」で閲覧できる登記簿(登記事項証明書)に記載された面積を基に土地を売買する方法です。
なので、実際に土地の面積を測ったりしません。
(測らないというよりも、測れないことが多いようですが・・)
先ほどの説明にあるように、登記簿の中にはかなり以前に登録された情報が基になっていることがあるので、土地によっては「登記されている土地の面積」と「実際の土地の面積」が大きく食い違うことがあるんです。
とくに、「売り買いされたことのない先祖代々の土地」や「利権関係がはっきりしないため調査の進んでいない都市部の土地」に多く、
「登記簿の面積」と「実際の面積」の剥離が大きい傾向があります。
土地の実測売買とは


じゃあ、土地って実際に買ってみないと広さが分からないんですか?

そんなことはありません。
次に紹介する「実測売買」という方法なら、「購入した土地の面積」と「契約書の土地の面積」が大きく異なることはないので、安心してください。
「公簿売買」のように、登記簿に記載された土地の面積ではなく、実際に測量した面積で土地を売買するのが、「実測売買」と呼ばれる方法です。
測量方法によっては多少の誤差が生じることもありますが、その差は僅かなので、「予定していた建物が入りきらない」なんてこともないでしょう。

ちゃんと測量すれば誤差が少ないなら、どんな土地でも実測してから販売したらいいのに・・
なんで、「公簿売買」なんて方法がまかり通るんですか?

それには理由があって、
土地の面積を確定するために必要な「境界確定測量」に、「多額の費用」や「手間」が必要になることがあるからなんです。
土地の境界確定測量とは


土地の持ち分を示すために、上の画像のような境界標を土地の境界(境目)に設置しているのをご存知ですか?
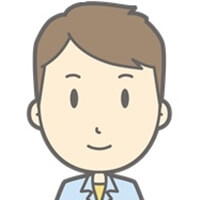
「コンクリート製」や「金属製」の境界標のことですか。
土地の四隅なんかに設置されているのを見たことがあります。

ちゃんと全ての境界標があるとイイんですけど・・これがないと話がややこしくなることが多いんですよね・・

あっ!ごめんなさい。つい心の声が・・
実は、この境界標が全て揃っていない土地も多く、お隣との境界がハッキリしないことがよくあるんです。
そんな際、その境界に関係する土地所有者の立会いの下、お互いに異議がないことを確認し、土地の面積を確定させる作業を「境界確定測量」と言います。
しかし、「境界確定測量」をしようにも、全ての土地の所有者が快く承諾してくれるとは限りませんし、それぞれが納得するまでに「多額の費用」や「多くの時間」が必要になることも少なくありません。
とくに、「土地の坪単価が安い地域」や「複数の所有者の土地と隣接している土地」では、「境界確定測量」に必要な「費用」や「時間」がデメリットとなってしまい、
やむを得ず「公簿売買」という売買方法に頼らざるを得ないことがあるんです。
後で差額を清算する併用売買とは

ですが、「公簿売買」による「デメリット」や「トラブル」を嫌う人も多く、
最近では、「公簿売買」と「実測売買」を併用した、「併用売買」と呼ばれる売買方法を取り入れている「物件」や「不動産会社」もあります。
「併用売買」とは、土地の契約自体は「登記簿に記載された面積」を用いるのですが、土地の契約後に実測を行い、その面積差を後で清算する土地の売買方法です。

このように、一口に土地の売買といっても、様々な売買方法があるんです。
後々のトラブルを防ぐためにも、事前に土地の売買方法の確認を忘れないようにしてくださいね。
中には買主から要望しないと、あえて詳しく説明しない不動産業者もいたりするので、用心するに越したことはありませんよ。

土地の売買方法って一つだけじゃないんだ・・
もし知らずに土地を購入してしまったら、大変なことになってしまうかもしれませんね。
家づくりに失敗しないように、少しずつでも学んでいきたいと思います。
土地の境界標の確認は必須!ーまとめ
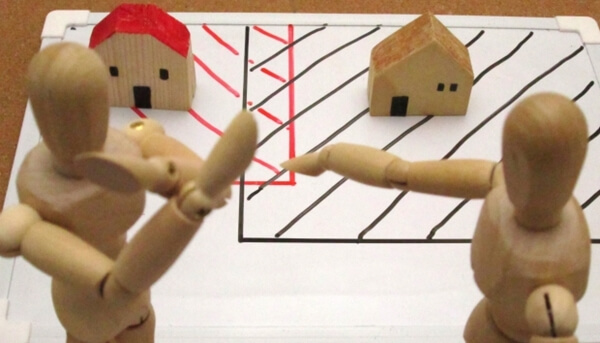

いくつか土地の売買方法について紹介しましたが、
家づくりに失敗しないためにも、土地の購入の際に心掛けてほしいことがあります。
それは、土地を契約する前に「境界標の有無」を確認することなんです。
先ほども申し上げましたが、土地の「所有権」や「面積」を主張するためには、「境界標」が大きな力を発揮します。
例えば、土地の売主が「土地の境界はこの石だから」なんて言っても、隣の土地の所有者がそれで納得してくれるかどうか分かりません。
ですが、「境界標」があれば、そんなトラブルに巻き込まれる危険性がかなり低下するんです。
というのも、土地を契約するまでは熱心な不動産営業マンでも契約したら最後、土地トラブルの解決まで積極的に動いてくれることは期待できません。
それに、土地の代金を全額払っていなくても、契約解除するには手付金を諦めなければならないことが多いんです。

注文住宅でよくある話なんですが、
土地購入の際に「境界標の有無」の確認を怠っていて、建物を配置する基準が曖昧になってしまうことがあります。
そのままでは工事が進められないので、お隣の土地の所有者の方に確認したりするんですが、それが元でトラブルになることも多いんですよね。

たしかに施主としては、これからマイホームを建てて住み続けるのに、お隣さんとのトラブルは避けたいですね・・
もちろん、大きなトラブルになることなく、スムーズに土地の境界が決まることもあります。
しかし、やはり餅は餅屋と言いますか、土地のことに関しては、住宅会社よりも不動産会社の方がたくさんのノウハウを持っているので、「時間」や「費用」の節約に繋がることが多いんです。
それに、土地を契約する前であれば、トラブル回避のために積極的に動いてくれる不動産営業マンが多いのも事実ですからね。

やっぱり土地の購入でも契約する前に確認を行い、事前に解決しておくことが大切なんですね。
トラブルには巻き込まれたくないので、前もって念入りに情報収集して学んでおきます!

おっ!やる気満々ですね。
私もお手伝いしますので、「質問」や「相談」があれば、気軽に声をかけてくださいね。
■ 「公簿売買」では、実際の土地の面積と大きく異なることも少なくない
■ 「境界確定測量」を行っておけば、後々の境界トラブルを防げる
■ 土地を購入する際は、境界標の有無の確認を忘れない